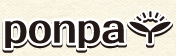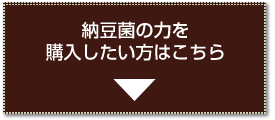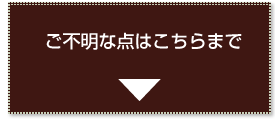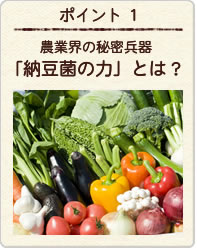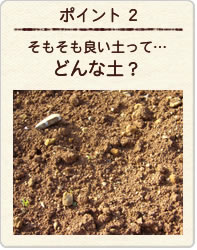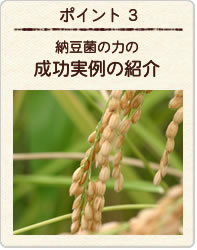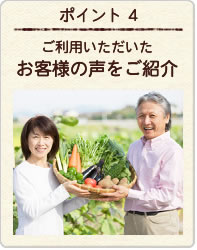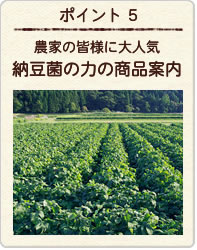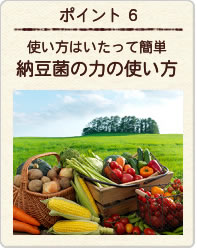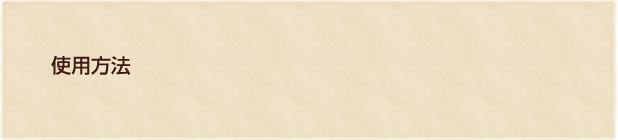
簡単だから人気があるのです
共通の注意事項
- 微生物の餌となる有機系の肥料も使ってください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(使用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 水に溶く際、納豆菌の力(粉末タイプ)を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力(粉末タイプ)を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- 水に溶いたものは使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。
微生物土壌活性剤『納豆菌の力(液体タイプ)』の使用方法
基本編(液体タイプ)
苗作り (トマト・ナス・ピーマン・しし唐・メロン・花卉他)
播種後に最初の水やり、もしくは発芽後に100?200倍の水で希釈した納豆菌の力をタップリとかける(発芽前の水やりは、種の流出にご注意ください)。
又は、100?200倍の水で希釈した納豆菌の力を、鉢植え時最初の水としてタップリとかける。(鉢植えの前日にタップリとかけておいても可)
定植時
100?200倍の水で希釈した納豆菌の力を定植時に育苗箱へ散布もしくはドブ漬けする。
又は、100?200倍の水で希釈した納豆菌の力を、株元へ最初の水代わりにかける。
購入苗の場合
苗が来てすぐに定植しない時は、鉢にも納豆菌の力を100?200倍の水で希釈しタップリかけておく。
定植時100?200倍の水で希釈した納豆菌の力を定植時に育苗箱へ散布もしくはドブ漬けするか、定植後100?200倍の水で希釈した納豆菌の力をタップリかける。
苗に使用する場合は最低でも定植前に一度処理して下さい。
セル苗の場合は500mlで50a分くらいの苗に、ポット苗の場合は10~20a分くらいの苗に処理が可能です。
その後、長期にわたり収穫する作物には
2?4週に1度300~1000倍に溶かして根元に散水するか、10aに対して200~500mlの納豆菌の力を潅水に混ぜる。
- 微生物の餌となる堆肥(有機物)も使ってください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
土づくり編(液体タイプ)
pH(ペーハー)が整っているのを前提とし、圃場全体に堆肥をすきこむ際に納豆菌の力を一緒にすきこみます。
割合としては10aに入れる堆肥量に対して納豆菌の力を200~500ml程度入れる。
又は、堆肥をすきこみ終わった後に納豆菌の力を300~1000倍の水で希釈し、圃場全体にたっぷりとかけて下さい。圃場の乾燥具合に応じて水の量を調整してください。
- 土の乾燥具合によって、倍率を調整してください。乾燥がひどい場合は規定倍率よりも更に濃度を薄く水を多めにして施用してください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
堆肥づくり編(液体タイプ)
堆肥2~3トン(10aに施与する量)に対して納豆菌の力50~500mlを混ぜ込んでください。熟成させる際に今までよりも熱を発する可能性があります。熱を帯びてきたら切り返しをおこなってください。
今まで同様のタイミングで圃場にすき込んでください。
大量に堆肥を作る際は、まず少ない量の山で一度発酵をさせ、それをもとの山に戻して混ぜ合わせるとさらに良い堆肥が作れます。
- 熱が発生したまま放置すると自然発火の恐れもありますので、必ず切り返しをおこなってください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
ぼかし肥作り編(液体タイプ)
米ぬか・油粕・魚粉・牛糞・豚糞・鶏糞などなんでも結構です。コーヒー粕やふすまなど、食品加工業から大量にでてくる産業廃棄物でも結構です。つまり原材料は有機物で、ある程度の窒素分を含むものならなんでもよいです。おがくず・木の皮・カンナ屑など木質は発酵・分解するのに時間がかかるので、避けたほうが良いです。
手に入る材料の中には、水分が多いもの、乾燥してパラパラのもの、粉末状、固形物などいろいろあります。固形物は小さめに砕く必要があります。この時混ぜ合わせた後の水分含量はできるだけ少ないほうがよいです。混ぜ合わせたあと、手で握って水が出てくるものは必ず腐ってしまいます。手で握って固まっても指で押すとパラパラと砕けるくらいが限度と思ってください。こんなバラバラに乾燥しているもので大丈夫か?と疑問に感じるかもしれませんが、ここで水を入れると絶対うまくいきません。水分含量で40%がちょうどよいです。
牛糞だと水分含量80%以上、オカラで85%くらいです。これを目安として、水分の少ない米ぬか・油粕・籾がらなどを混ぜ合わせてください。
水分含量に注意して手に入った材料を混ぜ合わせ、10aに施与する量に対し納豆菌の力50~500mlを混ぜ込んでください。納豆菌の力は均一に混ぜなければいけません。一度に有機物と混ぜるとうまく混ざりません。納豆菌の力とその10倍くらいの乾燥した発酵材料の有機物を混ぜ合わせます。それを大量(10倍くらい)の有機物に加えて混ぜ合わせてください。
- 土嚢袋に詰めるかブルーシートに広げ、雨の当たらないところで仕込んでください。
- シートに広げる際は、厚みに注意してください。夏なら50センチまで、気温が低ければ厚めに積んでください。
- 発酵温度は熱めの風呂を目安に、アチチと感じる程度が限界です。
- ボカシ肥のでき上る目安は、夏場なら10日前後、春秋なら2週間、冬なら1ヶ月程度です。
- 発酵を止めるには乾燥させてください。そのままで1年は使えます。土嚢袋を使った際は袋が通気性なので、発酵しながら熱で勝手に乾燥します。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤は絶対に同時使用しないで下さい。
- ボカシ肥は即効性で窒素含量も高いため、少量でもすぐに肥効があらわれます。追肥としての使用がお勧めです。
- ボカシ肥は施用してから数日以内に肥効が出はじめ、気温・地温によってちがってきますが、夏だと2週間くらい、春・秋だと3週間ほどで6割くらいの窒素を放出します。あまり過度に与えると窒素過多になるので注意してください。
- 堆肥に比べ発熱は少ないので自然発火の恐れは低いですが、あまりにも高温になっているときは必ず切り返しをおこなってください
水稲への使用方法(液体タイプ)
基本的使用方法
マット苗・ポット苗にかかわらず1~1.5葉期に納豆菌の力を100~200倍の水で希釈したっぷりかけておく。
プール方式の場合は少し多めに水の中に溶かして下さい。
殺菌剤との同時使用はやめてください。
どうしても殺菌剤を入れる場合は、使用後10日以上あけて100~200倍の水で希釈し箱へたっぷりかけて下さい。
田植え前の苗にもう一度100~200倍の水で希釈した納豆菌の力を散布あるいはドブ漬けしてから田植えをおこなってください。
最低でも田植え前の苗に一度処理して下さい。
この使用方法なら500mlで苗箱200枚(1ha)分くらいに処理が可能です。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
パンフレット掲載:長野県飯田市の片桐修さんの使い方
『納豆菌の力(液体タイプ)』を200倍希釈(100L)にし、定植前の苗箱にジョーロで散布。
散布量は苗箱の下から希釈液がしみ出る程度に散布しています。
この1回の処理でパンフレットに紹介している効果がでています。
この使用方法であれば500mlで苗箱200枚(約1ha)分くらいに処理が可能です。
果樹への使用方法(液体タイプ)
基本的使用方法
最初の年
1~3年の新植の場合は植穴もしくは植穴脇にも穴をあけそこに約10mlの納豆菌の力を入れて植える。
又は、植えてある木の周りに300~1000倍に希釈した納豆菌の力を雨降りの日もしくは雨の前日に散布して土(根)にしみこませます。
木が大きくなるにつれ、散布する範囲を広くしてください。
- いずれの場合も春、地温が14~15度以上になってきてから雨降りの日に撒くか、雨の前日に撒くか、撒いた後に水をかけて土中(根)にしみこませて下さい。
- 3月末より6月の梅雨あけまでにお使いください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 灌水設備がある所は、300~1000倍に溶いた納豆菌の力を根元から枝の伸びている範囲にタップリ撒水して下さい。その後は定期的に納豆菌の力を撒水する
微生物土壌活性剤『納豆菌の力(粉末タイプ)』の使用方法
基本編(粉末タイプ)
苗作り (トマト・ナス・ピーマン・しし唐・メロン・花卉他)
播種後に最初の水やり、もしくは発芽後に500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力をタップリとかける(発芽前の水やりは、種の流出にご注意ください)。
又は、500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力を、鉢植え時最初の水としてタップリとかける。(鉢植えの前日にタップリとかけておいても可)
定植時
500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力を定植時に育苗箱へ散布もしくはドブ漬けする。
又は、500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力を、株元へ最初の水代わりにかける。
購入苗の場合
苗が来てすぐに定植しない時は、鉢にも納豆菌の力を500〜1000倍の水で希釈しタップリかけておく。
定植時500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力を定植時に育苗箱へ散布もしくはドブ漬けするか、定植後500〜1000倍の水で希釈した納豆菌の力をタップリかける。
苗に使用する場合は最低でも定植前に一度処理して下さい。
セル苗の場合は100gで50a分くらいの苗に、ポット苗の場合は10~20a分くらいの苗に処理が可能です。
その後、長期にわたり収穫する作物には
2〜4週に1度1500~5000倍に溶かして根元に散水するか、10aに対して40~100gの納豆菌の力を潅水に混ぜる。
- 微生物の餌となる堆肥(有機物)も使ってください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。
土づくり編(粉末タイプ)
pH(ペーハー)が整っているのを前提とし、圃場全体に堆肥をすきこむ際に納豆菌の力を一緒にすきこみます。
割合としては10aに入れる堆肥量に対して納豆菌の力を40~100g程度入れる。
又は、堆肥をすきこみ終わった後に納豆菌の力を1500~5000倍の水で希釈し、圃場全体にたっぷりとかけて下さい。圃場の乾燥具合に応じて水の量を調整してください。
- 土の乾燥具合によって、倍率を調整してください。乾燥がひどい場合は規定倍率よりも更に濃度を薄く水を多めにして施用してください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。
堆肥づくり編(粉末タイプ)
堆肥2~3トン(10aに施与する量)に対して納豆菌の力10~100gを混ぜ込んでください。熟成させる際に今までよりも熱を発する可能性があります。熱を帯びてきたら切り返しをおこなってください。
今まで同様のタイミングで圃場にすき込んでください。
大量に堆肥を作る際は、まず少ない量の山で一度発酵をさせ、それをもとの山に戻して混ぜ合わせるとさらに良い堆肥が作れます。
- 熱が発生したまま放置すると自然発火の恐れもありますので、必ず切り返しをおこなってください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。
ぼかし肥作り編(粉末タイプ)
米ぬか・油粕・魚粉・牛糞・豚糞・鶏糞などなんでも結構です。コーヒー粕やふすまなど、食品加工業から大量にでてくる産業廃棄物でも結構です。つまり原材料は有機物で、ある程度の窒素分を含むものならなんでもよいです。おがくず・木の皮・カンナ屑など木質は発酵・分解するのに時間がかかるので、避けたほうが良いです。
手に入る材料の中には、水分が多いもの、乾燥してパラパラのもの、粉末状、固形物などいろいろあります。固形物は小さめに砕く必要があります。この時混ぜ合わせた後の水分含量はできるだけ少ないほうがよいです。混ぜ合わせたあと、手で握って水が出てくるものは必ず腐ってしまいます。手で握って固まっても指で押すとパラパラと砕けるくらいが限度と思ってください。こんなバラバラに乾燥しているもので大丈夫か?と疑問に感じるかもしれませんが、ここで水を入れると絶対うまくいきません。水分含量で40%がちょうどよいです。
牛糞だと水分含量80%以上、オカラで85%くらいです。これを目安として、水分の少ない米ぬか・油粕・籾がらなどを混ぜ合わせてください。
水分含量に注意して手に入った材料を混ぜ合わせ、10aに施与する量に対し納豆菌の力10~100gを混ぜ込んでください。納豆菌の力は均一に混ぜなければいけません。一度に有機物と混ぜるとうまく混ざりません。納豆菌の力とその10倍くらいの乾燥した発酵材料の有機物を混ぜ合わせます。それを大量(10倍くらい)の有機物に加えて混ぜ合わせてください。
- 土嚢袋に詰めるかブルーシートに広げ、雨の当たらないところで仕込んでください。
- シートに広げる際は、厚みに注意してください。夏なら50センチまで、気温が低ければ厚めに積んでください。
- 発酵温度は熱めの風呂を目安に、アチチと感じる程度が限界です。
- ボカシ肥のでき上る目安は、夏場なら10日前後、春秋なら2週間、冬なら1ヶ月程度です。
- 発酵を止めるには乾燥させてください。そのままで1年は使えます。土嚢袋を使った際は袋が通気性なので、発酵しながら熱で勝手に乾燥します。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤は絶対に同時使用しないで下さい。
- ボカシ肥は即効性で窒素含量も高いため、少量でもすぐに肥効があらわれます。追肥としての使用がお勧めです。
- ボカシ肥は施用してから数日以内に肥効が出はじめ、気温・地温によってちがってきますが、夏だと2週間くらい、春・秋だと3週間ほどで6割くらいの窒素を放出します。あまり過度に与えると窒素過多になるので注意してください。
- 堆肥に比べ発熱は少ないので自然発火の恐れは低いですが、あまりにも高温になっているときは必ず切り返しをおこなってください
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。
水稲への使用方法(粉末タイプ)
基本的使用方法
マット苗・ポット苗にかかわらず1~1.5葉期に納豆菌の力を500~1000倍の水で希釈したっぷりかけておく。
プール方式の場合は少し多めに水の中に溶かして下さい。
殺菌剤との同時使用はやめてください。
どうしても殺菌剤を入れる場合は、使用後10日以上あけて500~1000倍の水で希釈し箱へたっぷりかけて下さい。
田植え前の苗にもう一度500~1000倍の水で希釈した納豆菌の力を散布あるいはドブ漬けしてから田植えをおこなってください。
最低でも田植え前の苗に一度処理して下さい。
この使用方法なら100gで苗箱200枚(1ha)分くらいに処理が可能です。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。 (併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。)
- 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。
パンフレット掲載:長野県飯田市の片桐修さんの使い方
『納豆菌の力(液体タイプ)』を200倍希釈(100L)にし、定植前の苗箱にジョーロで散布。
散布量は苗箱の下から希釈液がしみ出る程度に散布しています。
この1回の処理でパンフレットに紹介している効果がでています。
この使用方法であれば500mlで苗箱200枚(約1ha)分くらいに処理が可能です。
果樹への使用方法(粉末タイプ)
基本的使用方法
最初の年
1~3年の新植の場合は植穴もしくは植穴脇にも穴をあけそこに約2gの納豆菌の力を入れて植える。
又は、植えてある木の周りに1500~5000倍に希釈した納豆菌の力を雨降りの日もしくは雨の前日に散布して土(根)にしみこませます。
木が大きくなるにつれ、散布する範囲を広くしてください。
- いずれの場合も春、地温が14~15度以上になってきてから雨降りの日に撒くか、雨の前日に撒くか、撒いた後に水をかけて土中(根)にしみこませて下さい。
- 3月末より6月の梅雨あけまでにお使いください。
- 納豆菌の力は生きています。殺菌剤・殺虫剤等との同時使用はしないで下さい。
(併用する際は最低10日ほど時間をあけてご使用ください。) - 希釈したものはその日のうちに使い切ってください。時間をあけると死んでしまいます。
- 灌水設備がある所は、1500~5000倍に溶いた納豆菌の力を根元から枝の伸びている範囲にタップリ撒水して下さい。その後は定期的に納豆菌の力を撒水する。
- 水に溶く際、納豆菌の力を一気に水に入れ放置すると固まりになります。水に投入後はすぐにかき混ぜてください。
- 納豆菌の力を水で拡散する場合、事前に少量の水でドロドロに溶かした後規定の倍数にして下さい。(一気におこなうと固まりができやすくなります)
- ジョーロ・動噴・灌水装置等を使って灌水する場合は、納豆菌の力液体タイプをご使用ください。粉末タイプは詰まる場合がありますので、一度確認後作業をおこなってください。詰まる場合は、水で溶いたものを3時間ほど放置し、メッシュの細かいもの(パンティストッキング等)で濾過したものをご使用頂くか、給水口にメッシュの細かいもの(パンティストッキング等)をまき、ろ過しながら使用してください。